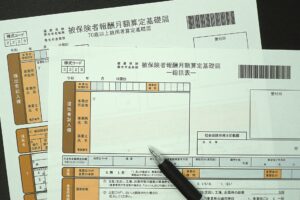~企業に求められる「柔軟な働き方」への対応~
近年、働き方の多様化や少子高齢化が進む中で、育児・介護に関する法改正が続いています。
2025年10月1日に施行される今回の改正では、企業が柔軟な働き方を実現するための制度を導入することが義務化されます。
本記事では、その主な改正内容と企業が対応すべきポイントをわかりやすくまとめます。
柔軟な働き方を実現するための措置が義務化
3歳以上で小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して、
以下の5つの措置のうち、2つ以上を導入することが義務化されます。
- 始業・終業時刻の変更(時差出勤)やフレックスタイム制
- テレワーク制度(原則として月10日以上、時間単位での利用が可能)
- 保育支援(保育施設やベビーシッターの手配・費用補助など)
- 養育両立支援休暇(年間10日以上、原則時間単位で取得可能)
- 短時間勤務制度(例:1日6時間勤務など)
制度設計にあたっては過半数代表者からの意見聴取が必要です。
すでに自社で要件を満たす制度を導入している場合は、そのまま運用を継続することも可能です。
現実的には、時差出勤や短時間勤務制度などは3歳未満に限らず運用している企業も多く、自社の実情に応じた制度設計が求められます。
制度の周知と利用意向の確認が義務化
3歳未満の子を養育する労働者に対しては、上記で選択した制度について個別に周知・意向確認を行う義務があります。
対象期間:
子どもの3歳の誕生日の1か月前までの1年間
周知内容:
- 事業主が導入する2つ以上の対象措置の内容
- 申出先(例:人事部)
- 残業免除・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
実施方法:
面談(オンライン可)、書面交付、FAX、メール等
※FAXやメールは、労働者が希望した場合のみ可
なお、利用を控えさせるような働きかけは認められません。
制度を適切に周知し、利用を後押しする姿勢が求められます。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取
さらに、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た際、
および子が3歳になるまでの間に、個別の意向聴取が必要になります。
聴取内容の例:
- 勤務時間帯(始業・終業時刻)
- 勤務地や就業場所
- 両立支援制度の利用期間
- 業務量や労働条件の見直しなど
方法は前項と同様に、面談や書面、メール等で行います。
まとめ:育児と仕事の両立を支える企業へ
今回の法改正では、単に休業制度を設けるだけでなく、
出産・育児に関する周知や意向確認など、具体的なケアの実施が義務化されました。
企業には、
- 柔軟な働き方を実現できる環境の整備
- 制度内容の明確化と従業員への周知
- 個別の意向聴取と適切な配慮
が求められます。
早めに制度設計や運用ルールの見直しを進めていきましょう。
小濱社会保険労務士事務所では、
制度設計・就業規則の見直し・社内説明資料の作成など、
企業の育児・介護支援体制づくりをサポートしています。
お気軽にご相談ください。